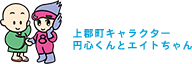お知らせ
最終更新日:2016年4月22日(金曜日) 13時46分
ID:2-3-9609-9504
印刷用ページ
足利幕府誕生のキーマン 赤松円心
中世の播磨を代表する武将・赤松円心(あかまつえんしん)を紹介
中世播磨の名族・赤松氏の祖にして、鎌倉幕府から室町幕府への政権交代に大きく関わった武将・赤松円心について紹介します。
赤松円心は、鎌倉幕府の領する荘園・播磨国佐用荘(現在の兵庫県佐用町・宍粟市・上郡町の一部)の有力武士で、幕府御家人とも考えられる宇野氏の一族・赤松家に生まれました。宇野氏は、佐用荘東の宇野荘(佐用町東部)出身で、領主の公家・久我家にあやかって村上源氏末裔と名乗っていたとみられます。
鎌倉時代の円心を含む宇野氏一族は、京の幕府出先機関の六派羅(ろくはら)探題と関りをもっていたといわれています。円心の住む赤松村は佐用荘の南端に位置し、山陽道に近い地の利を活かしながら、円心はいつしか一族全体を統率する力を蓄えていったとおもわれます。
当時の朝廷は持明院統と大覚寺統に分かれていましたが、大覚寺統の後醍醐天皇が皇統の独占を図り、両統迭立を支持する鎌倉幕府打倒の兵を挙げると、後醍醐天皇の皇子・護良親王の令旨に応え、苔縄城(上郡町苔縄)で挙兵しました。船坂山、高田(上郡町内)において幕府方の軍勢を破りながら山陽道を東上し、摂津・山城で六派羅勢と激戦を繰り広げたことが、『太平記』に詳しく描かれています。
そして、幕府方から寝返った足利尊氏勢とともに京を攻略し、建武政権の樹立に大功を挙げました。
その後、政権内部の対立から護良親王派として失脚、佐用荘に帰郷しますが、政権に反旗をひるがえした足利尊氏に味方して戦い、『梅松論』によると、窮地に立つ尊氏に大覚寺統と対立する持明院統の光厳上皇の院宣をもらうよう進言したといわれています。
院宣をもって九州で尊氏が兵を集めている間、新田義貞率いる建武政権の軍勢を、白旗城(上郡町赤松)に籠って約50日余り防ぎ止めました。やがて東上した尊氏勢とともに湊川の合戦で新田・楠勢を破り入京し、足利尊氏を征夷大将軍とする室町幕府の誕生にも大きく関わることとなりました。
円心はこれらの功で播磨国守護職に任ぜられ、各地で後醍醐天皇を奉じる南朝方と戦う一方、苔縄城の麓に法雲寺を建て、臨済宗の高僧・雪村友梅(せっそんゆうばい)を招いて開山とし、後に同寺に播磨国の利生塔を建立、戦乱の犠牲者たちの鎮魂につとめるなど、幕府の重鎮としてふるまいました。
宝林寺(上郡町河野原)にのこる赤松円心の坐像(兵庫県指定文化財)は、腰に太刀を佩き、剃髪しても家督を譲っていない半俗の出家者「沙弥(しゃみ)」のまとう五条袈裟(ごじょうけさ)を身に着けており、自らの書状にも一貫して「沙弥円心」と記すなど、齢50を過ぎた晩年期に武将として大活躍した円心の人生を物語っています。円心は観応元年(1350)、享年73歳で亡くなりました。
円心の三男則祐の子孫は惣領家として播磨・備前・美作3国の守護大名を務め、長男範資の「七条家」、次男貞範の「春日部家」など、他の一族も各地で栄えるなど、赤松氏は、中世を代表する名族のひとつとして後世に名をのこします。江戸時代の久留米藩主・有馬家は、則祐の子孫に当たります。
今でも赤松氏の末裔と伝えられる家は山陽路に多く、一族繁栄の基礎は、赤松円心によって築かれました。
※主な参考文献 高坂 好『赤松円心・満祐』 1970年 株式会社吉川弘文館
『上郡町史』第一巻 2008年 上郡町
お問い合わせ
教育総務課 総務・文化財係
電話 0791-52-2911
ファックス 0791-52-5523
メール syakai@town.kamigori.lg.jp
関連ファイル
関連リンク
カテゴリ
最終更新日:2016年4月22日(金曜日) 13時46分
ID:2-3-9609-9504
印刷用ページ
情報発信元
生涯学習課 生涯学習・文化財係
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-2911
ファックス:0791-52-6221